| |
|
|
|
 |
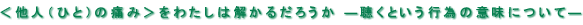 |
 |
推薦文
: 経済学部 大田 一廣 教授
|
|
もう13年も前になってしまった――およそ五千四百人余にものぼる死者をだしたあの阪神大震災
から、わたしはわたしなりに学んできた。奈良市内に住んでいたから、直接の大きい被害はなかったが、そのころ小学生だった息子も、いまでは君たちと同じ大学生になっている……。わたしが阪神大震災についてのいろいろな議論で、もっとも感銘をうけたものが何冊かある。震災直後の救援システムを的確な判断によって驚異的に構築した精神科医の中井久夫が編集した『1995年1月・神戸―「阪神大震災」下の精神科医たち』(みすず書房刊、1995年3月)や歌人塚本邦雄「拉がれしいのち五千餘 立春の氷裂けたる硝子の破片」一首を含む『悲傷と鎮魂―阪神大震災を詠む』(朝日出版社刊、1995年4月)、そして、ここで紹介する鷲田清一『聴くことの力』などだ。
|
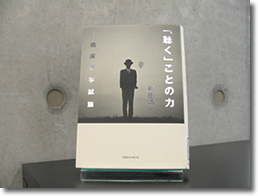 |
| TBSブリタニカ 1999年7月 |
きみたちもそう感じているように、普通は、見ず知らずの他人(タニン・ヒト)の話などとりたてて関心もないし、聴きたくもないだろう。だが、鷲田さんの紹介する「聴くという行為」の話をはじめて読んだ感動はいまでも忘れない――多分、なにかに感動して高揚し、あるいは涙して深い闇に沈むとき、<この私>の魂の瞬間の経験に、きみも反応するにちがいない。その話とは、大震災で深刻な衝撃をうけた被災者たちと“救援”のために現場にはいったヴォランティアの活動についてだ。
ヴォランティアの女性はなにをしたかというと、動揺し心も定まらぬ被災者――この女性は“自分の不注意によって最愛の子供を失った”と深い悲しみにある――が一方的に語る話を、頷いたり相槌をうったりするのではなく、またつぎの話題へと促したりもしないで、ただただ、ひたすら黙って聴くに聴き続けたというのだ。君たちも経験があるように、自分の話を友人や家族や教員(!)に聴いてもらって、“スッキリ”したことがあるだろう。
ヴォランティアの女性は、大震災のさなかに、耐えに耐えて耐え抜いてそれを実行したわけである。
鷲田さんは、この話を、相手(他人)の話を一方的に聴くという行為は、表面的にみると、ひどく受動的で<私>がいないと見られるかもしれないが、実はまったくその逆だという。他人の話をひたすら聴くという行為は、当事者のうち、聴く方は過大な忍耐とその忍耐に耐えようと決意するきわめて積極的な<私>なのであり、この聴く<私>にささえられて、他方の、語る被災者は“ほっ”としたにちがいない。被災者としての<私>がはっきりと<この私>へと返ったのかもしれないのだ。この場合、受身の姿勢が人と人のあいだで積極的な能動的役割を演じていることになる。<対話的コミュニケーションの効用>などと小賢しい言辞を弄ぶ人々もいるにはいる。だが、ここではむしろ聴くという<一方通行>こそ、親しみの濃厚な、しかも魂の清冽な交流が当事者のあいだにあったにちがいない。<対話>とはそういう沈黙の瞬間によって成り立っているのかもしれない。
鷲田清一は面白い人だから、場末の酒場やバーで酔ったお客の<どうでもよい話>をマダムが聴くでもなく聞いていて、酔客に応対する超絶技巧についても語っているが、このケースにも、膝を打つ人たちは多いだろう。ほかならぬわたしも、それで随分救われている!
わたしは、鷲田さんの本を読んで、中村草田男の俳句を想い出す――
・ひとを訪わずば自己なき男月見草
さて、来年、月見草はまた咲くだろうか、あるいは枯れ果てて朽ちてしまうだろうか?
|
|
鷲田 清一 (わしだ きよかず)
現在、大阪大学学長。専門は臨床哲学。精神や身体、国家にとどまらず、食生活、労働、京都案内、ファッション、アートなどにわたって多数の著書がある。
・1989年サントリー学芸賞受賞 『モードの迷宮』
・2000年桑原武夫学芸賞受賞 『「聴く」ことの力』
・2004年紫綬褒章受賞
|
|
| |
|
|
 |
|


