| |
|
|
|
 |
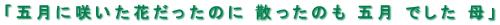 |
 |
推薦文
: 経済学部 大田 一廣 教授
|
|
寺山修司が逝ったのは1983年5月4日だったから、今年は歿後25周年にあたる。思潮社版『われに五月を』は寺山修司の三回忌のいわば「贈り物」(中井英夫)として復刊されたもので、冒頭に引いた「母」とは、修司の母・寺山ハツその人である。療養中の修司の写真が透けて見える中扉には、「五月に咲いた花」がハツの筆跡で書かれている。この「五月の花」はいかにも寺山修司の瑞々しい「きらめく季節」を髣髴とさせて余すところがない。先の戦争で夫を奪われ、ただひとりのわが子に寄り添い、ひたすら愛し理解しようと努めた母ハツの渾身の誄詞というべきだろう。
|
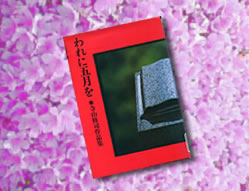 |
| 思潮社
1985年5月 |
『われに五月を』は、十八歳の寺山修司を『短歌研究』第二回新人賞特選「チエホフ祭」五十首(1954年11月)をもってデビューさせた編集長の中井英夫がネフローゼを病んだ修司のために、せめて生存中に一冊の書物をという涙ぐましい献身によって刊行した詩歌集である(初版、作品社刊、1957年)。巻頭の「五月の詩・序詩」で「二十歳 ぼくは五月に誕生した」と寺山修司は書いている。母・ハツのいう「五月に咲いた花」は幻想の真っ赤な花のはずであった。
ところで過日、古本屋めぐりの帰りに難波のジュンク堂に立ち寄った。人目のつきやすい書棚に“テラヤマ本”が、俳句・短歌から放送劇・演劇・映画・評論などさまざまなジャンルにわたって揃えられていた。――いまなお根強い人気だなと頷く一方、はたして誰が読むのだろうと思ったりもした。だが、芸術表現のほとんどの領域を自在に越境した寺山修司の真価はたぶん短歌にこそあるのではないか、わたしにはそう思われる。田中未知の編集によって陽の目をみた「歌の別れ」以後の寺山修司未発表歌集『月蝕書簡』(岩波書店刊、2008年2月)もまた、そう思わせる。
『われに五月を』から紹介しよう――ふと口遊むと、“青の時代”の光芒と瞬間の恥じらいがにわかに浮き立つような、いずれも人口に膾炙した歌(と俳句)である。
・とびやすき葡萄の汁で汚すなかれ虐げられし少年の詩を
・海を知らぬ少女の前に麦藁帽のわれは両手をひろげていたり
・そら豆の殻いっせいに鳴る夕べ母につながるわれのソネット
・一粒の向日葵の種蒔きしのみに荒野をわれの処女地と呼びき
・森駈けて来てほてりたるわが頬を埋めむとするに紫陽花くらし
「森番」
・マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや
・夏蝶の屍をひきてゆく蟻一匹どこまでゆけどわが影を出ず
「祖国喪失」
・目つむりていても吾を統ぶ五月の鷹
「燃ゆる頬」
晴れがましい羞恥、抑えがたき高揚と不遜なる自負、透明に輝く憧憬とエロス、母との愛憎半ばする肉の業、そしてテロルへのやや危険な衝動――十代の寺山修司がすでに、“青春”なるもののいっさいを詰め込んだ、ほとんど完結した言語世界を構築していたことに、あらためて驚嘆するほかはない。
寺山修司には第一歌集『空には本』(1958年)、第二歌集『血と麦』(1962年)、第三歌集『田園に死す』(1965年)、未刊歌集「テーブルの上の荒野」があり、あらたに『月蝕書簡』が加わったことになるが、なかでも『田園に死す』は「寺山修司の才能の完璧な、あるひは完熟した集成」(塚本邦雄)といってよいだろう。
・大工町寺町米町佛町老婆買ふ町あらずやつばめよ
・新しき仏壇買ひに行きしまま行方不明のおとうとと鳥
・亡き母の真っ赤な櫛で梳きやれば山鳩の羽毛抜けやまぬなり
・売られたる夜の冬田へ一人来て埋めゆく母の真っ赤な櫛を
・とんびの子なけよとやまのかねたたき姥捨以前の母眠らしむ
・濁流に捨て来し燃ゆる曼珠沙華あかきを何の生贄とせむ
・見るために両瞼をふかく裂かむとす剃刀の刃に地平をうつし
・降りながらみづから亡ぶ雪のなか祖父(おほちち)の瞠(み)し神をわが見ず
・吸ひさしの煙草で北を指すときの北暗ければ望郷ならず
『田園に死す』
いずれも、一首に「物語性」(吉本隆明)を封じ込んだ“掌編小説”の趣があり、主題もはっきりしていて実に分かり易い。母、家、望郷そして自立への屈折とアイロニーは、晩年の修司をも捉えて離さなかったといってよいと思う。
・面売りの面のなかより買ひ来たり笑いながらに燃やされにけり
・壜詰の蟻をながしてやる夜の海は沖まで占領下なり
『月蝕書簡』
純白の無垢の頁を切り裂き、別様の物語を紡ぎだすべき「剃刀の地平」には、いったい何が見え隠れしていただろうか。塚本邦雄をして「完璧な、完熟した集成」といわしめた『田園に死す』の「跋」は、ロートレアモン『マルドロールの歌』を引き合いにだしつつ、つぎのことばで結ばれている――「偉大な質問になりたい」。
寺山修司自身による自作短歌の朗読テープを聴きながら、わたしはいま、あの独特の訛りのなんともいえぬもの哀しさに囚われている。ふたたび――<みづからがひとつの質問に成る>とはどういうことか。
【なお、『われに五月を』にはほかに復刻版(日本図書センター刊、2004年)と文庫版(ハルキ文庫、角川春樹事務所刊、2004年)が、また諸歌集に「初期歌篇」を加えた『寺山修司青春歌集』(解説中井英夫、角川文庫、改版2005年)がある。】
|
|
|
寺山 修司
(てらやま しゅうじ) [1935―83]
詩人、歌人、作詞家、劇作家、シナリオライター、映画監督。31歳の時、演劇実験室「天井棧敷」設立。
・ 1954年第2回『短歌研究』新人賞受賞 『チェホフ祭』
|
|
| |
|
|
 |
|


