| |
|
|
|
 |
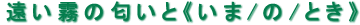 |
 |
推薦文
: 経済学部 大田 一廣 教授
|
ミラノに霧の日は少なくなったというけれど、記憶の中の霧には、いまもあの霧が静かに流れている。
|
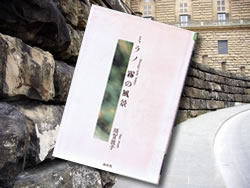
白水社刊 1990年12月 初版 |
これは、巻頭に置かれた「遠い霧の匂い」を締めくくる結びの文章である。
あの日あの時あの場所の「霧の匂い」を彼方から引き寄せ、そのひとつひとつを慈しみながら嗅ぎわけて、それらをいわば思い出の宝石箱に大切に仕訳しておくというような、須賀敦子の《青春》の凝集した精神と深い思索が、この本の全篇をおだやかに律している。プルーストの「記憶」や小林秀雄の「思ひ出」につながる《微細の歴史》に対するなみなみならぬ洞察と覚悟が須賀敦子の姿勢に脈打っているといってもよいかもしれない。
|
ミラノ育ちの夫は、霧の日の静かさが好きだった。”giò per i poumon”「ずうっと肺臓の奥深くまで」霧を吸い込むとミラノの匂いがするという方言の歌を彼はよく歌った。
|
「遠い霧の匂い」――須賀敦子にとって、すべてはこの霧から、霧の記憶のなかからはじまる。
カトリック左派のミラノの拠点だった「コルシア書店」の、ユダヤの人々に好意をもって接したイタリア人の夫との運命的な出会いと突然の死別、留学のためジェノヴァに上陸したとき――1950年代の西欧への留学の場合はながい船旅のすえ、マルセイユかジェノヴァに上陸するのが普通だった。鷗外や森有正はマルセイユに上陸したはずである――、そこではじめて迎えてくれ、その後も「びっしり、こまかい読みにくい字」で書かれた葉書を頻繁に寄せて、イタリアに留まってヨーロッパ文化に内在する思索へと彼女を向かわせた、先の戦争による過酷な収容所体験をもつ寡黙なマリア、夫を亡くして自失に襲われた彼女を「睡眠薬をのむよりは、喪失した時間を人間らしく誠実に悲しんで生きるべきだ」といましめてくれ、晩年は精神を病んで他者の世界を失った「幼稚園の子供のような真剣さ」を滲ませる、そういう背中を遺して逝ったガッティ、さらに「トリエステには/閉ざされた/ながい悲しみの日々/ぼくが自分を映してみる道がある」と詠う、彼女の夫も好きだったウンベルト・サバの詩との邂逅など、すでに遠い過去の人々の「匂い」が「遠い霧」として濃密に立ちこめて、《そのとき-そこに》自分の生(ビオス)が《だれか/なにか/とともに》確かに息づいていたこと、いな現にいま息づいていることを、端正な美しい文章で綴った『ミラノ 霧の風景』は、詩と死と史をめぐる《いま/の/とき》の思索への清新な試み(エセー)であり、文字通りの文学的エセーというべきものである。
無垢の魂と繊細な言語感覚をもち、流れるような日本語をもののみごとに操る須賀敦子(1929-1998)が惜しまれて逝ったのは、1998年3月のことだったから、今年はちょうど歿後10年にあたる。最後の仕事になった訳詩集『ウンベルト・サバ詩集』(みすず書房刊、1998年8月)の跋には、彼女自身の『トリエステの坂道』(1995年)の一部が《あとがき》に替わるようにして収められている。
|
なぜ自分はこんなにながいあいだ、サバにこだわりつづけているのか。二十年まえの六月の夜、息を引きとった夫の記憶を、彼といっしょに読んだこの詩人にいまもまだ重ねようとしているのか。(『トリエステの坂道』)
|
第一次世界大戦後のハプスブルク家の支配の崩壊とともにイタリアに復帰した北東部の、峻険な山の迫る国境の港町トリエステは、彼女がもっとも愛した「ふたつの世界の書店主」詩人サバの故郷であった。北イタリアとオーストリー・ウイーンとのふたつの文化の狭間に漂うトリエステの詩人サバの文学はそのまま、日本とイタリアとの、二元のあわいに立つ須賀敦子自身の生でもあったにちがいない。
端正な匂い立つ品、余すところのない措辞、流麗たる詩語、明快な構成などどれをとっても、日本語の可能性を、西行よりも新古今の藤原定家が好きというこのイタリア文学者が拓いたことは、文学愛好者や研究者を問わず、いまではおおくの読者が知るところとなっている。けれども、須賀敦子が日本の読書界に“とつぜん”立ち現われたのは、日本語によるはじめての文学的エセー『ミラノ 霧の風景』がふたつの大きな文学賞を受賞したときであって、このときすでに61歳になっていた。もっとも一部の目利きには、彼女のエセーや訳詩の冴えは目にとまっていたし、それにさきだってイタリアでは、文学の専門研究者としての評価は高く、鷗外・谷崎・川端など日本文学の紹介は、イタリア人の文学研究者も舌を巻くほどの“完璧なイタリア語”であったという。
1953年にフランス政府給費留学生としてパリに渡った須賀敦子は、翌年の夏に、比較文学の研究に必要な、ふたつめの外国語としてイタリア語をあの友人マリアに導かれてペルージャで学んでいるが、この体験がクリスチャンとしての信仰の深化と純化、イタリア人との結婚、さらにはイタリアとの文学的・宗教的・精神的な深い繋がりを彼女に与えつづけることになったのだった。ちなみに“戦後”――という言葉には《第二次世界大戦、とりわけ太平洋戦争以後》なる注釈が必要なご時世とあいなったけれども――はじめてのフランス政府給費留学生(1950年)が、ヨーロッパ精神の「経験」と「倫理」にかんする深い洞察にみちた思索を紡いだ書簡体の哲学的エセー『バビロンの流れのほとりにて』(1957年)の著者森有正(1911-1976)であり、須賀敦子は森の三年後に渡仏したことになる。
こういう須賀敦子の経歴はともかく、本書を充たす珠玉のエセーにひとり一人、ちょくせつにあたっていただきたいと思う。私の日本語では、須賀敦子の清冽な精神の趣をとうてい伝え難い。ここでは選びに選んで、「鉄道員の家」を紹介しておきたい。須賀敦子の夫はミラノの、やや貧しい鉄道員の息子だった――。
|
映画を見て、私は夫が死んで二十年以上ものあいだ、これを見ていなかったことの不思議さに打たれた。映画をかたちづくっている言葉はすべて、あの鉄道線路の横の家で覚え、聞いた、私のイタリア語の原点にたつものばかりだった。/もしこの映画を見ていたら、おそらく私は自分が溶けてしまうほどの、もういちど立ち上がれないほどの衝撃を受けただろう。
|
須賀敦子が最愛の夫を亡くして二十年以上の後に観たというこの映画は、ピエトロ・ジェルミ監督・主演の『鉄道員』(1956年)であり、この鉄道員家族の住む「アパートメントは/ミラノ・ローマ本線の線路沿いの夫の実家そっくりだった」。そして、映画の家長とおなじように、「夫の父親も、ある日、仕事を終えて帰ってきて、ちょっと横になる、と言ったきりだった。」
この文章に接して私は、ネオ・レアリズモの名作『鉄道員』のバックに流れる哀愁を湛えたあの曲を、ふと耳にしたような気がした――。
|
|
須賀敦子
(すが あつこ) [1929‐1998]
昭和後期-平成時代のイタリア文学者,随筆家。昭和4年2月1日生まれ。フランス,イタリアに留学し,イタリア人と結婚。昭和46年夫の死去で帰国。上智大教授となり,13年間のイタリア生活を回想した「ミラノ
霧の風景」で平成3年女流文学賞,講談社エッセイ賞。
―講談社『日本人名大辞典』Japan
Knowledgeデータベースより |
|
| |
|
|
 |
|


