| |
|
|
 |
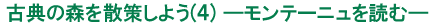 |
 |
推薦文
: 図書館長 和田 渡 (経済学部 教授)
|
エラスムスの『対話集』(二宮 訳、中央公論社)を愛読していたのがモンテーニュ(1533~1592)である。両者とも結石で苦しみ、その経験について語っている。モンテーニュは、判事や裁判官などを経て、1571年には法曹の世界から退き、農園経営をしながら、読書と思索の日々を過ごした。その成果が『エセー』に結実し、1580年に初版が出た(第1巻と第2巻)。1581年の秋にはボルドーの市長に選ばれ、2期務めた。1588年には第3巻がパリで出版された。加筆修正は最後まで続けられた。画期的な新訳による『モンテーニュ エセー抄』(宮下志朗訳、みすず書房、2003年)には、全部で11のエセーが収められている。同じ訳者による『エセー』全巻の翻訳が進行中で、現在(2011年)4冊目までが白水社から刊行されている。
冒頭の「読者に」でモンテーニュは言う。「読者よ、わたし自身が、わたしの本の題材なのだ。こんな、たわいのない、むなしい主題のために、きみの暇な時間を使うなんて、理屈にあわないではないか。では、さらば。」(4頁)謙遜のふりをしながらの、自分を話題にする試みの開始宣言だ。 |
 |
とはいえ、この試みは自己の虚飾化や自惚れのおしつけ、あつかましい自画自賛とは無縁である。エラスムスが痴愚神の仮面をかぶって、人間の愚かさ、馬鹿馬鹿しさを愉快な口調で語ったとすれば、モンテーニュは、なによりもまず自分自身の愚かさについて率直に、余裕のある調子で語る。
「経験について」というエセーのなかでも、同じように述べられる。「わたしは他の主題にもまして、自分自身を研究する。これがわたしの形而上学であり、自然学なのだ。」(134頁)目を自分の外部に向け、自分以外のものについて語る主体から、目を自分の内部に向け、自分自身を語る主体への転換だ。この転換によって、きわめて刺激的に見える自己認識が獲得される。「ばかなことをいったとか、したとわかっても、それだけでは仕方ない。自分がおろかな存在にすぎないことを悟る必要がある。このほうが、よほど豊かで、たいせつな教えだと思う。」(137頁)鏡に映ったわれわれの歩き方は、しばしばぶざまで滑稽にしか見えない。これは肉眼で確認できる。ところがモンテーニュは、肉眼のレヴェルの観察にはとどまらない。自分の心眼(内的な視線)を通じて観えてくるものを追いかけるのである。そこで掴まえられるのが、他ならぬ自分の考え方の未熟さや数々の愚行なのである。
モンテーニュは、自分が愚かで、へまをやらかす存在でしかないという認識を決して手放すことはない。それを拠点にしながら、一方で、自分の性格や食事、セックス、排泄、病気、病気による身体の変化といった生活のこまごまとしたことについて語り、他方で自分の目が捉える他人の姿や、書物のなかの人間、世の中の出来事などについてもえんえんと語ることを止めない。インディオの文化を論じながら、ヨーロッパ人の一部に蔓延した偏狭な自国中心主義と、相手の文化や伝統を圧殺する「野蛮」を厳しく諌めて、モンテーニュの慧眼が現実を射抜いたものも含まれている。
『エセー』の全体を貫く主題は「自分」の存在である。しかし、その細部では実に多様なことが語られているのだ。たとえば、この「経験について」というエセーには、若者向けの発言がいくつもあって面白い。ニーチェを刺激したと思われるような文章を引こう。「精神が満ちたりてしまうのは、それが縮んだり、弛緩した証拠である。高邁な精神ならば、自足することなどなく、常に望みを高く抱いて、自分の力を越えたところを進んでいく。そして、自分の法を越えて、飛躍するのだ。前進もせず、急ぎもせず、窮地にもおちいらず、また、ぶつかることもなければ、くるくる変わることもないならば、それは半分しか生きていない証拠だ。」(125頁)ニーチェの自分を超えて進めという「超人」思想の先取りである。現在の自分を不断に乗り越えて、いまある自分とは違う自分をつくっていかなければ生きているとはいえないという若々しい主張だ。低いレヴェルの自己満足や安易な自分との妥協を排して、緊張感を保ち、強い意志を持って、高みを目指すべきだという、若者への激励でもある。
「若者ならば、自分の活力を目覚めさせて、それにカビが生えたり、いじけてしまわないように、生活のルールに揺さぶりをかけなくてはいけない。(中略)若い人はときには羽目をはずしてみるのがいい。さもないと、ささいな道楽で、身をもちくずしてしまうし、人とのつきあいでも、気むずかしくて、不愉快な人間になってしまう。」(156-157頁)狭く窮屈な枠に自分を閉じこめず、常に柔軟であれという忠告だ。平々凡々な生に自足していると活力を失い、年若くても老人のようになってしまう。時に乱痴気騒ぎの熱狂に身をゆだね、時に快楽におぼれるのもよい、単調な生とは断固として訣別せよという強いメッセージである。周りばかりを気にして萎縮し、用心深く他人との距離を測り、決して羽目をはずさず、失敗することもなく、痛い目に会うこともなく生きるなど論外だということであろう。
「青年たちになによりも奨めたいのは、活動的で、覚醒していることだ。生きることは運動にほかならない。」(184頁)モンテーニュの目にも、不活発で、呆けてしまっている青年が少なくないと映ったのだろうか。彼が生きた時代に、若年性痴呆症の若者がいたとは思えないが。「生きることは運動すること」、これは当たり前のことに見えるだけに、不断あまり意識しない。生きることが運動と結びつかない場合も少なくない。たとえば、肉体の運動を怠れば身体は固くなるし、精神の運動を欠けば、しなやかに生きることが難しくなる。活力が失われ、覚醒からは遠ざかる。若くても、すっかり呆けてしまうのだ。その状態をよしとしなければ、心身両面の運動を不断に自分に課して、自分を鍛えることしかない。だが、それが容易ではないのだ。ついつい運動を忘れて、惰性的になり、眠りこんでしまい、どんな状態になっているのかさえ気づかなくなる。運動不足で、自分の体の重みに負けて歩行が困難になる場合もあれば、頭の体操不足で、知的な体力がみるみる衰えてしまう場合もあるのだ。
モンテーニュは、肉体を敵視し、肉体的な快楽を軽蔑する輩を憎み、肉体の鍛錬を大いに強調し、同時に、精神の運動をよりしなやかにする訓練の大切さをも訴えた。肉体と精神を分離し、後者に力点を置こうとした輩に対しては、両者の相互交流を力説した。「精神が、重い肉体を目覚めさせて、活性化し、肉体が、軽い精神にストップをかけて、落ち着かせるようにしようではないか。」(223頁)心身が共に合い携えた共同作業こそ、モンテーニュが期待したものだ。
自分自身に関する研究を大切に考えた人の言葉はこうだ。「われわれの悪癖のうちでもっとも野蛮なものは、自分という存在をないがしろにすることだ。」(214-215頁)自分をないがしろにしないとは、自分の心と身体をいたわるということだ。両者はしばしば苦痛と快楽の源泉である。生きるということは、まずは、心身合一体としてのわれわれが苦しみと楽しみの両面を経験するということだが、それにとどまらず、その経験を意識して生きるということでもある。「苦痛と快楽というのは、いわばふたつの泉なのであって、都市にせよ、人間にせよ、はたまた動物にせよ、いつ、どちらの泉から、どれほど汲み出すのかをしっかりわきまえているならば、とても幸福な存在といえる。」(216頁)モンテーニュ流の幸福のすすめと言ってよい。要は、心身の経験のさなかにあって、醒めているということだ。心と身を分離し、身を遠ざけることではない。
「自分の存在を、正しく享受することができるというのは、ほとんど神のような、絶対的な完成なのだ。われわれは、自分自身のありようをいかに使いこなすのかわからないから、他の存在を探し求めるのだし、自分の内側を知らないために、自分の外側に出ようとする。」(226-227頁)われわれの悪癖としての野蛮を避け、自己のもとにとどまり、自分とのつき合いを大切に考えた人ならではの語り口だ。
モンテーニュに興味がある人には、モンテーニュの人柄や思想にとどまらず、彼が生きた乱世の時代をも活写した堀田善衛の『ミシェル 城館の人』(集英社、1991-1994年)三部作がおすすめだ。第一部は「争乱の時代」、第二部は「自然 理性 運命」、第三部は「精神の祝祭」というタイトルがついている。保苅瑞穂の『モンテーニュ私記 よく生き、よく死ぬために』(筑摩書房、2003年)は、『エセー』との十数年に及ぶつきあいから生まれた、芳醇なワインのような味わい深い本だ。読み返すたびに、違う味に出会える。
|
| |
モンテーニュ【Michel
Eyquem de Montaigne】 [1533-1592]
フランスの思想家。豊富な知識と深い人間性省察に基づく主著「随想録」は、モラリスト文学の先駆として後世に大きな影響を与えた。
”モンテーニュ【Michel Eyquem de Montaigne】”, デジタル大辞泉, ジャパンナレッジ
(オンラインデータベース), 入手先<http://na.jkn21.com>, (参照 2011-01-24)
|
保苅瑞穂
(ほかり-みずほ) [1937-]
1937年、東京に生まれる。東京大学文学部仏文科卒業、同大学院人文科学研究科仏語仏文学専攻博士課程中退。東京大学大学院総合文化研究科教授を経て現在、獨協大学外国語学部教授。著書に『プルースト・印象と隠喩』(筑摩書房,1982)、『野田弘志・写実照応』(共著,求龍堂,1994)、『プルースト・夢の方法』(筑摩書房,1997)。訳書に『逃げ去る女』(プルースト,講談社,1978)、『プルースト全集』(共編・共訳,筑摩書房)、『事典プルースト博物館』(監修,筑摩書房,2002)など。―奥付より
|
|
| |
|
|
 |
|


