| |
|
|
 |
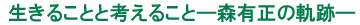 |
 |
推薦文
: 図書館長 和田 渡 (経済学部 教授)
|
内田義彦と同じように、個人がきちんと自分の目で見て、自分の頭で考え、自覚的に生きることの可能性について模索し続けたのが森有正である。人間の自主性、自立性を強調した森は、世間体や周囲の人間の視線を気にして生き、相手の地位や肩書きに応じて話す言葉や態度を変えることの多い日本人を繰り返し批判した。夏目漱石のイギリス留学からちょうど50年後の1950年に、森有正はフランスに給費留学した。船旅でマルセイユに着いた。夏目は2年ほどで帰国したが、森は当初の1年で帰国するという予定をずるずると先延ばしにした。帰国を促す同僚の声に応えず、日本に残した妻子とも別れ、そのままパリに居ついて、パリで帰らぬ人となった。
夏目は、イギリスでの生活になじめず、自閉的状態のなかで悶々として日々を過ごし、神経衰弱にも苦しんで日本に戻った。留学前の森は、パリには何か手に負えないようなものがあると予感して留学を恐れてもいたが、パリで暮らし始め、徐々にデカルトやパスカルを生んだパリという都市の魅力に目覚めた。フランス人の思考や行動様式にも関心を持つようになった。だがなによりも、自分が生きること、経験することの問題に行きあたった。パリは、困難な思索をおしまいまで生きることを森に強いることになったのである。パリは運命の街になった。 |
 |
夏目と森にとって、留学という経験は決定的な意味を持った。帰国した夏目は教師を辞めて、作家としての困難な道を歩き始めたが、『明暗』執筆の途中で病に倒れた。森は硬質な学術論文を書く研究者から、哲学的なエッセーや書簡、日記を書き続ける思索者へと変わり、思索の途上で客死した。異国の地で自分にぶつかるという出来事が、二人のその後の歩みに決定的な屈曲をもたらしたのである。
『思索と経験をめぐって』(講談社学術文庫)は、「霧の朝」「変貌」「木々は光を浴びて」という森の代表的なエッセー、「ルオーについて」と題する書簡体のエッセー、「経験について」という講演記録から成っている。感覚を重んじ、パリの街と風景のなかで思索した森ならではのタイトルだ。森の思索のキーワードは、経験と思想である。経験は事物との直接的な接触としての感覚を起点とし、思想は経験を言葉にもたらす試みの最終的な帰結である。森は「経験」に自分自身の生を重ね、経験と類似の概念である「体験」には、自分が好まない生の要素を見て遠ざけた。森によれば、体験は偶然的、機械的に増える自然な過程である。体験は、平板、空虚で、掘り下げられ、深められるという契機を含まない。体験のなかで体験それ自身が顧みられることが少ない。それに対して、経験は自己の自己への抵抗を含む過程である。経験の渦中では、自分に耐えて生きる、自分に目覚めて在る、自分の傾向に逆らって存在することが必要となる。そのことを通じて、経験はゆっくりと変貌し、深まっていくのである。体験は「長さ」によって、経験は「質」によって測られる。森は言う。
「『経験』というのは、ある一つの現実に直面いたしまして、その
現実によって私どもがある変容を受ける、ある変化を受ける、ある
作用を受ける、それに私どもは反応いたしまして、ある新しい行為
に転ずる、そういう一番深い私どもの現実との触れ合い、それを私は
『経験』という名で呼ぶ・・・。」(173頁)
要するに、現実との直接的なかかわりを心身の深いレヴェルで受け止めて、孤独な生を真摯に生きるということだ。あるいは、感覚的に与えられるものが自分のなかで発酵するのを忍耐強く待ち、それが言葉へとつながる局面をただ一人で身をもって生きるということだ。森がリルケから学んだ態度だ。その態度は、「私たちは今日もまた昨日のように各自の暗黒な経験の坑道を掘り進めていくほかはないのでしょう。というのはわれわれは人の達したところを土台にして出発することはできないからです。自分の経験は自分の経験でしかないのだ」(163頁)という言い方にも端的に示されている。「自己本位」を強調した時期の夏目漱石の姿と重なって見える。両者ともに、右顧左眄せず、自己に徹する道を選ぼうとしているのだ。経験が深まり、成熟へと向かう可能性は、この道の途上に開けているのかもしれない。
森有正の経験についての考え方や生き方を知るには、同じ著者による『いかに生きるか』(講談社現代新書)と『生きることと考えること』(講談社現代新書)が役に立つ。前者は、キリスト教主義の大学での四つの講演をまとめたものである。個人の自立を妨げる日本の社会に対する批判と、個人に自覚を促す主張が鮮明である。経験については、「はじめに」で次のように述べられている。
「私には深まりが大切なのである。深まりとは人間経験の深まりで
ある。私にとって経験とは現実そのもの以外の何ものでもなく、しか
も経験であることによって、現実には無限の深まりが可能であり、神
にさえ到りうるのである。」(4頁)
「深まる」という言い方は曖昧で、理解しにくいものとも思える。しかし、たとえば晩秋には季節の深まりがしみじみと感じられることがある。人間の経験も注意して、心をこめて生きるときに、経験の只中で深まりといったものが感受されるのかもしれない。森によれば、経験が深まるということは、空しくしか響かないような言葉の使い方が減って、よく響く言葉が発せられるようになるということだ。そのためには言葉と現実のかかわりについてよく考えて生きなければならない。言葉をどのように定義するかという問題が課せられてくる。借り物の言葉や奇をてらった言葉で他人を幻惑することを慎重に避けて、言葉が意味するものを自分のなかで確認する作業が必要になるのだ。孤独な作業である。だが、そこを起点としなければ、経験が深まることはないのだ。経験の深まりと変貌、それが森有正の生涯の課題であった。
『森有正全集』(筑摩書房)を底本として編まれた『森有正エッセー集成』[全5冊](ちくま学芸文庫)がある。みずみずしいエッセーや手紙、仏文日記の翻訳などが含まれている。
森のエッセーや日記、人間性について論じたものは何冊かあるが、辻邦生の『森有正 感覚のめざすもの』(筑摩書房、1980年)が森の生涯と思想を最もよく伝えている。辻は「あとがき」で述べている。「フランス文学に恩師渡辺一夫先生の面影が重なっているように、私のパリにはつねに森先生の影が濃く落ちている。私にとってパリの魅力も、パリの孤独のおそろしさも、先生を通して入ってきたものだった。」(169頁)
最近では、『世界の中心で、愛をさけぶ』の著者、片山恭一が、『どこへ向かって死ぬか 森有正と生きまどう私たち』(NHK出版、2010年)という森有正論を書いている。NHKの番組「知る楽 こだわり人物伝」のために書かれたテキストが基になっている。
|
|
|
森有正
【もり-ありまさ】[1911-1976]
昭和時代のフランス文学者、哲学者。
明治44年11月30日生まれ。森有礼(ありのり)の孫。パスカル、デカルトなどの近世フランス哲学を専攻し、昭和25年東大助教授在職中に渡仏。28年東大を辞してパリに定住し、国立東洋語学校、パリ大東洋学部で日本語、日本文化を講じる。47年から4年間パリ日本館館長。「遥かなノートル・ダム」以下一連の著作で「経験」の意味を説いた。昭和51年10月18日死去。64歳。東京出身。東京帝大卒。著作はほかに「パスカルの方法」「デカルト研究」「経験と思想」、エッセイに「バビロンの流れのほとりにて」など。
【格言など】体験と異なる本当の経験は正しい理想の上に立つものである(「霧の朝」)
”もり-ありまさ【森有正】”, 日本人名大辞典, ジャパンナレッジ (オンラインデータベース), 入手先<http://www.jkn21.com>,
(参照 2011-06-22)
|
|
| |
|
|
 |
|


