| |
|
|
 |
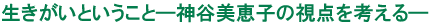 |
 |
推薦文
: 図書館長 和田 渡 (経済学部 教授)
|
森有正は、「生きること」を経験と思想の問題に結びつけて考え続けた。森にとって、「生きること」は、何よりもパリにおける自己の経験の諸相を見つめ続け、経験の深まりのなかで考えぬくことと重なっていた。それに対して、神谷美恵子は、病院のなかで「生きること」を「生きがい」の問題と結びつけて考え続けた。『生きがいについて』(著作集
1、みすず書房、1980年)には静かな情熱に支えられた彼女の思索が息づいていて、心打たれる。内容は、「生きがいを感じる心」「生きがいをうばい去るもの」「生きがい喪失者の心の世界」「新しい生きがいを求めて」「精神的な生きがい」などから成っている。現在は、著作集から選択して編まれた『神谷美恵子コレクション』(全5巻)がある。
今日の日本では、「健康・生きがい開発財団」がつくられ、「健康生きがいづくりアドバイザー」、「生きがい情報士」といった資格も得られるようだ。生きがいを、他人に提供すべきもの、他人からあてがわれるものと考えている人が少なくないということだ。しかし、「生きがい」という言い方に、今日の福祉政策的な意味とはまったく違う意味をこめて用いたのは神谷美恵子である。生きがいを他人とのつながりのなかで見出すことができれば、 |
 |
あるいは、一人一人が自分でつくっていくことが可能であれば、それが最も望ましいであろう。とはいえ、事態は単純ではない。過酷な現実が、生きがいを見出すことや、自分でつくることを困難にする場合も数知れないのだ。神谷が心を寄せるのは、生きがいを奪われた人、生きがいを見出せない状況に追いやられた人々であった。そうした人々がどうすれば生きがいを見出して生きていくことができるのだろうか、神谷の生涯は、この問いに答えていくために歩まれた。
一般的に生きがいがもっとも切実な問題となるのは、おそらくまだ職業や将来の方向が定まらない時期を生きる者にとってであろう。社会人として世に出る前には、誰もが多かれ少なかれ、何をして生きたらよいのか分からずにとまどう。神谷は言う。「青年期は一般に、もっとも烈しく、もっとも真剣に生の意味が問われる時期である。若いひとたちに日頃接している者ならば、だれでもおぼえがあろう。いったいどうして勉強などしなくてはならないのか、どうして生きて行かなければならないのか、どんな目標を自分の前においたらよいのか、と不安と疑惑にみちたまなざしで問いつめられたことを。(中略)ところがその青年たちも大人になると、いつしか生存の意味を問うことを忘れ、ただ生の流れに流されて行くようにみえる者が多い。」(36頁)大人になると、日々の忙しい生活に追われて、青年期の不安に満ちた問いは忘れ去られてしまうのだ。
しかし、長い一生の間に、ふと自分の生きがい何かと考えたり、思い悩んだりすることもあると神谷は言う。その時に発せられる問いが以下の四つにまとめられている。
1. 自分の生存は何かのため、またはだれかのために必要であるか。
2. 自分固有の生きて行く目標は何か。あるとすれば、それに忠実に生きているか。
3. 以上あるいはその他から判断して自分は生きている資格があるか。
4. 一般に人生というものは生きるのに値するものであるか。(33-34頁)
生きがいを感じて生きている人とはどんなタイプか。神谷の答えはこうである。「自己の生存目標をはっきりと自覚し、自分の生きている必要を確信し、その目標にむかって全力をそそいで歩いているひと―いいかえれば使命感に生きるひとではないであろうか。」(38頁)使命感を持って生きた人物として、シュヴァイツァとミルトンがあげられている。
世の中には、生きがいの問題が麻疹のように一過性のもので終わる人もいれば、ある日ふと、自分の生きがいが問題となり、それが契機となり、シュヴァイツァやミルトンのように、使命感に貫かれた生涯を歩んだ人もいる。
しかし、生きがいを求めても得られない人や、その問題が、苦しみや悲しみ、痛みに結びつく場合もある。神谷がいつも気にかけていたのは、深刻な病にかかり、生きがいを失った人、難病で生きがいを奪われた人、生の意味感を喪失した人たちのことであった。他方で、神谷は、絶望の淵からあらたな生きがいを得て立ち直る人にも注目している。神谷は、絶望的な病という極限を生きる人たちに、ハンセン病患者を隔離・収容した愛生園という施設で精神科医として働くなかで出会った。
深刻な病にかかった人たちの生きる姿勢、苦しみに打ちひしがれる姿を目にし、時には自暴自棄になって落ち込んでしまっている人と接するなかで、神谷の内省が繰り返される。ふとひとつの恐ろしい問いが心をよぎる。「『熱こぶ』で呻吟しているひと、精神の病のために絶望や虚無のなかにおちこんでいるひと、高齢のためにあたまが働かなくなり、ただ食欲だけになってしまったようなひとなど。こういうひとには、もはや生きがいを求める心も、それを感じる能力も残されていないのではないか。こういうひとにもなお生きる意味というものがありうるのであろうか。」(267頁)残酷な結末につながりかねない問いだ。神谷は、この問いに対して、宗教的な答えを与えている。「人間の存在意義は、その利用価値や有用性によるものではない。野に咲く花のように、ただ『無償に』存在しているひとも、大きな立場からみたら存在理由があるにちがいない。」(268頁)
さらに、病むことのない人はいないという見方が深められる。「五体満足の私たちと病みおとろえた者との間に、どれだけのちがいがあるというのだろう。私たちもやがて間もなく病みおとろえて行くのではなかったか。(中略)大きな眼からみれば、病んでいる者、一人前でない者もまたかけがえのない存在であるにちがいない。」(同頁)どんな人であれ、「もとをただせばやはり『単なる生命の一単位』にすぎなかったのであり、生命に育まれ、支えられて来たからこそ精神的な存在でもありえたのである。また現在もなお、生命の支えなくしては、一瞬たりとも精神的存在でありえないはずである。」(269頁)贈り物としてのいのち、われわれを支える根幹としてのいのちに根ざした視点が、静かな言葉で語られている。生きていることは、どんな状態であれ、等しくいのちを与えられて生かされてあることだという認識の強調である。
本書は、「病や苦難にみまわれたひとの心の世界という角度から、生きがいに関係した人間性の事実を少しでも探ろうとしたにすぎない」(274頁)と神谷は述べる。しかし、この本を読む誰もが、患者の心の世界の出来事を描いた神谷の記述を通して、人間の生きがいについての思索にいざなわれることは間違いないだろう。人間の生きる形は無限で、多彩である。自分なりの生きがいを得て生きられれば、あるいは、自分以外の誰かのために、自分以外の何かのために生きられれば幸いであろう。とはいえ、生きがいがかなう生は稀である。神谷が共感をこめて描いた人のように、生きがいを持てず、生きがいを奪われて生きていかざるをえないことの方が多いのだ。そうした生の現実を見つめ、考えることは、自分の生、他人との結びつき、いのちについて考える豊かな試みにつながっていく。
|
|
|
神谷美恵子【かみや-みえこ】[1914-1979]
昭和時代の精神科医。
大正3年1月12日生まれ。前田多門の長女。神谷宣郎の妻。昭和33年から47年までハンセン病療養施設長島愛生園の精神科に勤務。患者の行動と心の関連を分析して独自の「生きがい論」を確立した。38年津田塾大教授。昭和54年10月22日死去。65歳。岡山県出身。東京女子医専(現東京女子医大)卒。著作に「人間をみつめて」「生きがいについて」。
”かみや-みえこ【神谷美恵子】”, 日本人名大辞典, ジャパンナレッジ (オンラインデータベース),
入手先<http://www.jkn21.com>, (参照 2011-07-26)
|
|
| |
|
|
 |
|


