| |
|
|
 |
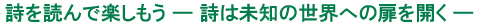 |
 |
推薦文
: 図書館長 和田 渡 (経済学部 教授)
|
言葉は、目には見えないものを観えるものにする魔法の効果を持つ。言葉は、見える世界と見えない世界に無数のつながりをもたらす。言葉が言葉を呼び、言葉と言葉が響き合い、練り上げられて詩が生まれる。書かれた詩は、読み手が現れない限り、物理的なものでしかない。しかし、読み手がページをめくるとき、言葉が蘇り、読み手の経験にあらたな変化や喜びを与える。詩を読むことは、言葉との接触と言葉の再生という経験を通じて、自己を新しくすることでもある。詩を敬遠する人は、自己の更新という貴重な機会を失い、詩を読む楽しさからも遠ざかってしまう。「詩は、そして言語は、意思疎通の手段であるばかりか、情熱や快楽の源泉でもあり得る―。」(J.L.ボルヘス、鼓 直訳『詩という仕事について』(岩波文庫、2011年、13頁)詩への感受性を開くことで、言語を介した無類の快楽が味わえるのだ。
今回は、情熱や快楽、驚異や憧憬を与えてくれるばかりでなく、世界や人間についての新鮮なヴィジョンを提示する詩をいくつか紹介しよう。
インドの詩人、ラビンドラナート・タゴール(1861~1941)は、 |
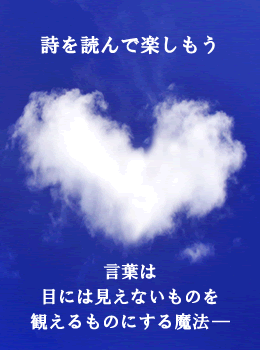 |
スケールの大きい詩をいくつも残した。およそ100年前に、アジア人としては初のノーベル文学賞を受賞した。『タゴール 死生の詩』(森本達雄編訳、人間と歴史社、2002年)には、英詩人ウイリアム・イェイツを特に感動させたという『ギタンジャリ』(ベンガル語で「歌のささげもの」という意味)のなかから20の詩が選ばれている。次がそのひとつだ。 |
昼となく夜となく わたしの血管をながれる同じ生命の流れが、世界をつらぬいてながれ、
律動的に鼓動をうちながら 躍動している。
その同じ生命が 大地の塵のなかをかけめぐり、無数の草の葉のなかに歓びとなって萌え出で、
木の葉や花々のざわめく波となってくだける。
その同じ生命が 生と死の海の揺籠のなかで、潮の満ち干につれて ゆられている。
この生命の世界に触れると わたしの手足は輝きわたるかに思われる。そして、いまこの刹那にも、
幾世代の生命の鼓動が わたしの血のなかに脈打っているという思いから、わたしの誇りは
湧きおこる。(29-30頁)
|
いのちを讃える言葉の響きが美しい。わたしを支えるいのち、わたしに受け継がれた幾世代のいのち、森羅万象を貫いて流れるいのち、いのちの脈動が世界を躍動させている。物も、草花も、動物も人も、いのちに祝福され、いのちの歌を歌っているのだ。
『ギタンジャリ』の全詩を読みたい人には、同じ訳者による『ギタンジャリ』(第三文明社、1994年)がおすすめである。こちらにはイェイツの序文と、英文がついている。
タゴールはありとあらゆるものに宿るいのちを寿いだが、人間のいのちの営みを力強い調べで歌ったのがアメリカの国民的詩人とも言われるウオルト・ホイットマン(1819~1892)である。代表作が『草の葉(上・中・下)』(酒本雅之訳、岩波文庫、1998年)である。30代の半ばに出版された。労働組合運動、選挙権の拡大運動といった、1930年代から40年代にかけての民衆の政治活動が活発になった時代に生きたホイットマンの思想や心情がこの詩集にこめられている。「『自分自身』をわたしは歌う」という詩を次にあげよう。
|
「自分自身」をわたしは歌う、素朴で自立した人間を、
それでいて「民衆の仲間」、「大衆のひとり」という言葉もわたしの口ぐせ。
頭のてっぺんから爪先までいのちの営みをわたしは歌う、
顔つきばかり脳髄ばかりを「詩神」は愛でず、すべてが揃った「人体」こそ遥かに尊い
宝のはず、
「男性」ばかりか「女性」もひとしくわたしは歌う。
情熱、脈搏、活力、すべてにおいて測りしれぬ「いのち」をそなえ、
奔放自在な振舞いができるよう神聖な法則どおりに造られた、
陽気で「新しい人間」をわたしは歌う。(上巻、47-48頁)
|
メキシコの詩人のオクタビオ・パス(1914~1998)は、言葉の自在な組み合わせによって、世界の多様な相貌に迫った。いのちの存在たちの接触も詩になった。次にあげる桑名一博訳による「二つのからだ」(『祝婚歌』所収、谷川俊太郎編、書肆山田、1981年、42-43頁)は、「対の関係」を生きる身体のつかの間の生態を照射した詩である。言葉が喚起するイメージが鮮やかに浮かび上がる詩だ。
|
むかいあう二つのからだ
あるときは夜の海の
二つの波。
むかいあう二つのからだ
あるときは夜の砂漠の
二つの石。
むかいあう二つのからだ
あるときは夜の底で
からみあう根。
むかいあう二つのからだ
あるときは夜の稲妻の
二つの刃。
むかいあう二つのからだ
あるときは虚空に落ちる
二つの星。
|
オクタビオ・パスの鋭敏な言語意識によって紡ぎ出される詩の世界では、言葉が闇を切り裂く一瞬の光のようにきらめいて、現実の断面をくっきりと照らし出す。突出した言葉が交差して、跳ね上がり、裂け、鳴り響いている。言葉が、太古の原初自然、宇宙と現代の人間の内部空間を貫いている。『オクタビオ・パス詩集』(真辺博章編・訳、世界現代詩文庫23、土曜美術社出版販売、1997年)が出版されているので、詩の言葉の持つ力に触れてみてほしい。
|
|
|
ラビンドラナート・タゴール
【Rabindranath Tagore】[1861~1941]
インドの詩人・小説家・思想家。インドの近代化を促し、東西文化の融合に努めた。ベンガル語で作品を書き、一部を自ら英訳。1913年、ノーベル文学賞受賞。詩集「ギーターンジャリ」、小説「ゴーラ」など。
”タゴール【Rabindranath Tagore】”, デジタル大辞泉, ジャパンナレッジ (オンラインデータベース), 入手先<http://www.jkn21.com>,
(参照 2012-01-25) |
ホイットマン
【Walt Whitman】[1819~1892]
米国の詩人。自由な形式で、強烈な自我意識、民主主義精神、同胞愛、肉体の賛美をうたった。詩集「草の葉」、論文「民主主義の展望」など。
”ホイットマン【Walt Whitman】”, デジタル大辞泉, ジャパンナレッジ (オンラインデータベース),
入手先<http://www.jkn21.com>, (参照 2012-01-25) |
|
オクタビオ・パス
【Octavio Paz】[1914~1998]
メキシコの詩人・批評家。シュールレアリスムの影響を受ける。1990年ノーベル文学賞受賞。詩集「世界の岸辺で」「言葉のかげの自由」、詩論「弓と竪琴」など。
”パス【Octavio Paz】”, デジタル大辞泉, ジャパンナレッジ (オンラインデータベース), 入手先 . <http://www.jkn21.com>,
(参照 2012-01-25)
|
|
| |
|
|
 |
|


