| |
|
|
 |
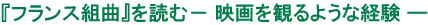 |
 |
推薦文
: 図書館長 和田 渡 (経済学部 教授)
|
昨年の秋に『フランス組曲』(野崎歓、平岡 敦訳、白水社)が出版された。やわらかな響きのするタイトルだが、第1部「6月の嵐」は、ドイツ軍の侵略を恐れてパリを脱出する多数の市民を描いた「戦争もの」である。全体で5部の大作が構想され、第2部の「ドルチェ」(音楽用語で、「甘い感じで」という意味)までしか書かれなかったが、後世にまで残る未完の傑作となった。小説を読む幸福が味わえる一冊である。
この本の著者イレーヌ・ネミロフスキーは、1903年にキエフで生まれ、ロシア革命の後に一家でフランスに移住したユダヤ人である。第二次大戦が勃発し、夫、娘二人と地方の田舎町に避難したが、1942年にドイツ警察の命令を受けたフランス人憲兵によって逮捕され、アウシュヴィッツに送られて殺された。1年後に、夫も同じ運命をたどった。彼女は娘に形見として膨大な原稿を残した。近い将来の死を予測して、緊迫した状況下で書き綴られたものだ。父は長女にこういい残したという「決して手放してはいけないよ、この中にはお母さんのノートが入っているのだから」。(552頁)長女は逃亡生活のなかでも、ノートの入った小型の重いトランクを手元から離さなかった。 |
|
この原稿は、60年以上の歳月を経て出版された。「20世紀フランス文学のもっともすぐれた作品のひとつ」と評価され、2004年に死後受賞としては初のルノードー賞(ゴンクール賞、フェミナ賞などと並ぶ文学賞のひとつ)を受賞した。全世界で約350万部という売り上げを記録しているという。
『フランス組曲』の第一部と第二部は、1940年の11月から、逮捕されるまでの1年半あまりで書かれた。ドイツ軍による占領下という事態のなかで翻弄され、狼狽し、右往左往した身近な人物たちの行動が描きだされている。非常時には、平時にはみえない人間の心がむきだしになる。けだかいもの、いやしいもの、あらあらしいもの、おぞましいものがみえてくる。イレーヌは、戦争という状況のなかでうごめく人間のふるまいになによりも強い関心をよせて描いた。
しかし、それだけではない。1942年の6月のノートにこうしるされている。「決して忘れてならないのは、いつか戦争は終わり、歴史的な箇所のすべてが色あせる、ということだ。1952年の読者も2052年の読者も同じように引きつけることのできる出来事や争点を、なるだけふんだんに盛り込まないといけない。トルストイを読み返すこと。その描写は他の追随を許さない。歴史的ではない描写。私が特に力を入れるべきなのもそこだ」(492頁)。目の前で起きている歴史的な出来事に対峙する小説家の覚悟が、トルストイの『戦争と平和』を意識して書きとめられている。戦争を傍観しえたトルストイとは異なり、「燃え上がる溶岩の上で仕事をしている」(557-558頁)と自覚していたイレーヌは、今経験していることを「あたかも百年前の出来事であるかのように眺めなければならない」(557頁)と自戒している。作家ならではの距離感覚だ。
イレーヌは、映画的な手法に興味をもった作家であるが、『フランス組曲』にはそれが存分にいかされている。「1戦争」は、開戦以後、初めて爆弾を落とされた日の翌朝のパリ市民と街の描写から始まる。まるで映画を観ているかのように、目の前に映像が浮かんでくる。パリの街はこう描かれる。「警戒警報が鳴り響く。消灯は行き渡っていた。だが、六月の澄んだ黄金色の空の下では、どの家、どの通りも見とおせた。セーヌ川はあらゆる光のかけらを寄せ集め、それを多面鏡のように百倍にもして反射するかのようだった。覆いの不十分な窓、薄暗がりの中できらめく屋根、かすかに輝く扉の金具の尖端、なぜかほかのところより長く灯っている赤信号。セーヌ川はそれらの光を引き寄せ、つかまえ、波間に戯れさせた」(10頁)。
この作品では、人間のふるまいが透視されるだけではない。自然の移ろいや動物たちへのまなざしもこまやかだ。「六月の夕べの優しい光は、あたりに広がったまま消えようとしなかった。それでも刻々と光は揺らめきながら弱まり、微かになっていき、あたかも毎瞬、大地にむかって名残惜しげに愛情を込めて別れを告げているかのようだった。窓際にすわった猫は、物悲しい様子で澄んだ緑の地平線を眺めていた」(21頁)。第20章は全体が猫へのオマージュであり、ところどころで作者が雄猫に変身して筆を進めている。「雄猫は半ば目を閉じて、自分が強烈な甘い匂いの波にひたされるのを感じていた。それは最後まで咲き残った少しばかり腐敗臭のするリラの花の匂い、樹木をめぐる樹液の匂い、暗く新鮮な土の匂い、獣、鳥、モグラ、ハツカネズミなど、あらゆる獲物の匂い、毛や血の放つ麝香のような匂いであり、とりわけ血の匂いだった・・・・・・」(139頁)。
第28章では、ジャンヌがつぶやく。「私たちはいま、恐ろしい状況にいるのよ。まるで大きな穴にむかって進んでいるようなもので、逃げようのないまま、一歩ごとに距離は縮んでいく。耐えがたいわ」(232頁)。彼女は憤然と叫ぶ。「いったい苦しむのはどうしていつでも私たちなの?私たちのような人間、普通の人間、しがない庶民ばかりが苦しまなければならないの?戦争になって、フランが下がって、失業だの危機だの革命騒ぎだのが起こっても、ほかの人たちはうまく切り抜けている。私たちだけがいつでも押し潰されるんだわ。なぜなの?私たちが何をしたっていうの?私たちがすべての罪をあがなわなければならないのよ」(233頁)。
第2部の「ドルチェ」は、ドイツ軍に占領された町での人々の日常や、ドイツ軍兵士とのかかわりを描いたものである。町のいたるところには、夜間外出や火器所持の禁止などを告げる貼り紙が張られ、「違反者は死刑に処す」という警告文が二重線で強調されている。敵を恐れ、憎む人もいれば、本音を隠して愛想よくふるまう人もいる。男たちが戦地にかりたてられて不在となった町で、ドイツ兵に惹かれる娘も出てくる。「ドルチェ」の核となるのは、リュシルというフランス人の既婚女性とドイツ兵ブルーノのつかのまの恋とその終わりである。ふたりの感情の揺れ動きが巧みに描かれている。ブルーノの弾くピアノ曲にリシュルが感応する場面が切なくも美しい。戦後のフランスではタブーとされたテーマだ。第22章では、戦争を見つめる作者の人間観が語られる。「だれもが知るように、人間とは複雑な存在だ。いくつにも分裂していて、ときには思いがけないものが潜んでいる。けれども人の本質が見えるには、戦争という時代、大きな激動の時代が必要なのだろう。それはもっとも情熱を掻き立て、もっとも恐ろしい光景だ。もっとも恐ろしいというのは、より真実の姿だから。海を知っていると自負するには、穏やかなときだけでなく嵐の海も見なければならない。嵐のなかで人間を観察した者だけが、人間の何たるかを知りえるのだ。その人だけに、己の何たるかがわかる」(469頁)。
イレーヌはアウシュヴィッツから生きてフランスに戻ることはなかった。強制収容所での実態や、極限状況における人間の行動や心理を描いていまも読みつがれるものには、ヴィクトールE.フランクルの『夜と霧』(新版、池田香代子訳、みすず書房、2002年)や、エリ・ヴィゼールの小説『夜』(新版、村上光彦訳、みすず書房、2010年)などがある。『夜と霧』は、「20世紀を代表する一冊」とも評される。若いときにぜひ読んでほしい。プリーモ・レーヴィの『アウシュヴィッツは終わらない あるイタリア人生存者の考察』(竹山博英訳、朝日選書、1980年)も、人間を見る目を鍛えてくれる。序のあとに「若者たちに」というメッセージがくわえられている。ドイツ政治思想史に詳しい宮田光雄の『アウシュヴィッツで考えたこと』(みすず書房、1986年)もおすすめの一冊である。
|
| |
イレーヌ・ネミロフスキー
(Irène Némirovsky) [1903-1942]
フランスのロシア人女性作家。キエフ生まれで、ロシア革命後フランスに亡命した。1942年ナチスに逮捕され強制収容所で死亡。フランス語で書き、小説『ダヴィド・ゴルデル』David
Golder(1929)によって一躍有名作家となった。『舞踏会』Le Bal(30)、『孤独の酒』Le
Vin de solitude(35)など、享楽的、刹那(せつな)的な風潮の1930年代を色濃く反映した小説で、快楽に溺(おぼ)れる人々の悲劇と、大人に反抗する子供たちの抗議と幻滅を、フランス的な明晰(めいせき)な文体で鋭く描き出した。
”ネミロフスキー イレーヌ”, 世界文学大事典 (下川茂) , ジャパンナレッジ (オンラインデータベース)
, 入手先<http://www.jkn21.com>, (参照 2013-01-28)
|
|
|
|
 |
|