| |
|
|
 |
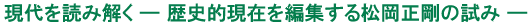 |
 |
推薦文
: 図書館長 和田 渡 (経済学部 教授)
|
『千夜千冊番外録 3・11を読む』(平凡社、2012年)は、稀代の読み手松岡正剛が「歴史的現在」という言い方で過去とつながる現在を見つめつつ、現在にいたる過去の歴史の細部を現在の視点から編集する意図のもとで、3・11以後に読みこんだ60冊の本の内容と考察の一部をまとめたものである。その狙いは、「事故と損傷の正体の真っ只中にあえて身を突っ込んで、新たな意味を再発見すること」(12頁)である。松岡は、3・11の意味が十分に掘りさげられないままに、隠蔽されていく状況に抗して、読んで考えるに値する何冊もの本を鋭い切り口で紹介している。現実に起きたこと、現に起きていること、これから起きるであろうことを理解し、熟考するための羅針盤となる本たちだ。冒頭の「小さな絆創膏」でこう書かれている。「ポール・ヴィリリオが『これからの時代は事故からしか新たな展望は生まれない』と言い、ジャン=ピエール・デュピュイが『いまや津波の体験が新しい形而上学を生むしかあるまい』と指摘したように、われわれは損傷の渦中から新哲学を掬ってくるべきなのである」(12頁)。 |
|
この本は、歴史的な現在に対する五つの視点から編集されている。第1章が「大震災を受けとめる」、第2章は「原発問題の基底」、第3章は「フクシマという問題群」、第4章は「事故とエコとエゴ」で、最後の第5章が「陸奥と東北を念う」である。第1章では大地震、大津波に襲われて生き延びた人々の記録や、被災地で報道を続けた人々の報告や写真を本にしたものが何冊も紹介されている。「また来ん春と人は云ふ」のなかでは、鈴木比佐雄他編『鎮魂詩404人集』(コールサック社、2010年)から何人かの生々しい、心を突き刺してくることばが数行ずつ抜き出されている。いずれも、沈思黙考と鎮魂の時間を促してくる(39~48頁参照)。「あのときの新聞記者たちの七転八倒」では、河北新報社『河北新報のいちばん長い日』(文藝春秋、2011年)における、記者たちの狼狽と奮闘のさまが紹介されている(71~74頁参照)。
第2章の冒頭では、松岡が「日本の原子力社会史の“原典”」(98頁)とみなす、吉岡斉『新版 原子力の社会史 その日本的展開』(朝日新聞出版、2011年)の内容が7ページに渡って紹介されている。第Ⅰ期(1939~53):戦時研究から禁止・休眠の時代から、第Ⅱ期(1954~65):制度化と試行錯誤の時代、第Ⅲ期(1966~79):テイクオフと諸問題噴出の時代、第Ⅳ期(1980~94):安定成長と民営化の時代、第Ⅴ期(1995~2010):事故・事件の続発と開発利用低迷の時代を経て、第Ⅵ期(2011~):原子力開発利用斜陽化の時代にいたる歴史的な経緯が簡潔にまとめられている(99~105頁参照)。高木仁三郎の『原発事故はなぜくりかえすのか』(岩波新書、2000年)も松岡の熱い思いがこもった紹介文である。高木は、原子力が文明であっても、とうてい文化にはなりえないと確信していたという(139頁参照)。
第3章では、高村薫『新リア王 上下』(新潮社、2005年)が取り上げられ、阪神淡路大震災を経験した高村のインタビュー発言が引用されている。「これは経験しないとわからないことですが、突然、世界がひっくり返るんですよ。足元が抜けるみたいに、今まで立っていた地上がなくなってしまう。それくらい、地震というのは怖い。そういう揺れを経験すると、それまで何十年と信じてきたものや価値観が一切合財なくなります」(188頁)。
第4章では、ポール・ヴィリリオ『アクシデント 事故と文明』(青土社、2006年)の紹介内容が特に濃い。この本の主張は、「21世紀の意識は事故[によってのみ際立つしかないだろう」という一文につきるだろうと断言されている(238頁参照)。松岡によれば、かつてトルストイやトーマス・マンやヘミングウェイは戦争によって知性と表現力を試されたが、今やわれわれは事故によってそれらを試されている(239頁参照)。ヴィリリオの発言が引かれる。「『事故とは、創造にして失墜であり、隠されていたものを白日のもとに晒すという意味で、ひとつの発明なのである』」(239頁)。
第5章では、「陸奥の歴史の奥に封印された蝦夷と征夷大将軍の実情を浮き彫りにした本」(425頁)が集められている。梅原猛『日本の深層 縄文・蝦夷文化を探る』(集英社文庫、1994年)、赤坂憲雄『東北学へ 1 もうひとつの東北から』(講談社学術文庫、2009年)、森崎和江『北上幻想 いのちの母国をさがす旅』(岩波書店、2001年)などである。地域の現在を過去の歴史と重ねて捉えることのむずかしさと面白さを教えられる章である。
「あとがき」で、松岡は日本の言論界では「ヒロシマ」や「事故」や「ツナミ」を思索の渦中にとらえて、そこから正体不明の新哲学を絞り出そうとする試みは少ないと述べつつも、3・11とそれ以降の社会についての思想的な成果がこれからアタマをもたげてくることに期待したいと結んでいる(429頁参照)。
中村征樹編『ポスト3・11の科学と政治』(ナカニシヤ出版、2013年)は、松岡の期待につながる本である。本書は、科学技術と社会とのかかわりを考察する「科学技術社会論」という学際的な研究分野で活躍する研究者の論文を集めたものである。科学技術の社会への影響、科学技術と人間の関係などについて、社会学、人類学、哲学、政治学、歴史学に固有な観点から考察されている。中村は「はじめに」でこう述べる。「科学技術社会論は、学問的な多様性を内包しながら、共有する問題関心をめぐって議論を精緻化するなかで発展してきた」(viii頁)。
第1章「食品における放射能のリスク」(神里達博)は、3・11以後の食品の放射能汚染問題を取り上げ、市民の不安と対応策の有無、行政側の対応と情報公開の信頼性の度合いといった問題について検討している。第2章「奪われる『リアリティ』 低線量被爆をめぐる科学/『科学』の使われ方」(調麻佐志)は、100ミリシーベルト未満の低線量被爆に関する専門家の「安全」説と、市民の側の「不安」を対比させ、背後に潜む問題を浮き彫りにしている。第3章「科学的根拠をめぐる苦悩 被害当事者の語りから」(八木絵香)は、JR福知山脱線事故の被害者の語ることに耳を傾け、被害者の健康不安や苦しみの実相に迫り、補償に関する過酷な現実にも目を向けている。「科学的フレーム」と「当事者フレーム」に対する向き合い方が問われている。第4章「科学技術をめぐるコミュニケーションの位相と議論」(田中幹人)は、科学技術に関する専門家と非専門家とのコミュニケーションのあり方を問うている。第5章「複合的災害、その背景にある社会」(標葉隆馬)は、東日本大震災における被害の規模や性格によって生じてくる諸問題や、「復興」の政治性に注目して考察している。第6章「原子力事故の『途方もなさ』をいかに理解するか ハンナ・アーレントの近代批判を導きとして」(平川秀幸)は、ハンナ・アーレントの考え方を手がかりにして現代の科学技術の性格を明らかにしている。アーレントの文章が引用されている。「物理学者は、原子核の操作が途方もない破壊力を秘めているのを十二分に自覚しながらも、その方法を知るとすぐさま、ためらいもなく核分裂に取りかかった。この単純な事実は、まさに、科学者としての[科学者は、地球上に人類が生きのびるのかどうか、ひいては地球そのものが存続するかどうかについてすらまったく気遣っていないことを証明している」(264頁)。アーレントは、なによりも経験の意味を問うことが大切だと考えた。松岡が取り上げた本『ツナミの小形而上学』(嶋崎正樹訳、岩波書店、2011年)の著者、ジャン=ピエール・デュピュイは、アーレントの思想に強い共感を示しているひとりだ。
『ポスト3・11の科学と政治』は、3・11以後の状況と真摯に格闘する、大半が比較的若い研究者たちによる意欲的な論文集である。今後の一層力のこもった論考が、現実の変革につながることを期待したい。
|
| |
松岡
正剛 (まつおか-せいごう) [1944-]
京都生まれ。編集工学研究所所長・イシス編集学校校長。1971年、雑誌「遊」創刊。1980年前後に編集工学を確立し、多様なジャンルでプロデュース・監修・演出を手がける。著書に『白川静』(平凡社新書)、『松岡正剛
千夜千冊』(全7巻+別巻1、求龍堂)、『17歳のための世界と日本の見方』(春秋社)、『多読術』(ちくまプリマ-新書)、『法然の編集力』(NHK出版)など多数。―本書奥付より
|
|
|
|
 |
|