| |
|
|
 |
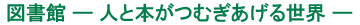 |
 |
推薦文
: 図書館長 和田 渡 (経済学部 教授)
|
アルベルト・マングェル、原田範行訳『読書の歴史-あるいは読者の歴史-』(新装版、2013年、柏書房)は、読書の魅力、面白さ、刺激的効果などについて縦横無尽に語る圧巻の一冊である。マングェルは、1948年にブエノスアイレスに生まれ、当地とロンドンで教育を受けた。英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語など数ヶ国語を駆使する作家、批評家として世界的に著名である。
「『読書の歴史』新版に寄せて」で、マングェルは人間を「本質的に読む生き物」であると定義しつつも、その特徴が失われつつある現代をこう批判する。「私たちは陳腐で安易なことにそそのかされ、読書を中断する娯楽を発明してしまいます。そして、貪欲な消費者と化し、新しいものだけに関心を持って過去の記憶には目もくれなくなってしまうのです。もはや知的行為は権威を奪われ、つまらない行いや金儲けの欲望に取って代られます」(iv頁)。「世界を結ぶ無線通信の幻想」(同頁)にかられ、無限の情報を追いかける忙しさと、ゆっくりと落ち着いてページをめくる余裕とは相容れない。最新の電子機器は人間の時間を細切れにし、やせ細らせるが、本を読む時間は思考力と想像力が絡みあって豊かに実ってくる。 |
|
しかし、実る時間を生きることはむずかしくなるばかりだ。「金銭的な野心を持った技術者たちによって作られた現実の体験をシュミレートする電子製品」(vii頁)に誘惑されて、干からびた時間のなかへ落ちていくのだ。マングェルによれば、産業中心の世界は、強欲で過剰な開発、過剰な消費、過剰な生産、無限の成長によって脅かされている(同頁参照)。それゆえに、彼は読書への期待をひかえめに語る。「一冊の本(あるいはカテドラル)へ穏やかな敬意を払うことで、もしかしたら私たちは立ち止まって内省し、誤った選択肢やばかばかしい楽園の約束を越えることができるかも知れません」(同頁)。
本書はひねった構成になっている。「最後のページ」から始まり、<読書すること>と<読者の力>が続き、「見返しのページ」が締めくくりに置かれている。本文には、「陰影を読む」「黙読する人々」「絵を読む」「一人で本を読むこと」「未来を読む」「書物泥棒」「禁じられた読書」「書物馬鹿」といった、博覧強記の著者ならではの文章が満載で、本をめぐる目くるめく世界へと連れていかれる。すぐれた作家や詩人の読書観もいたるところにちりばめられていて、飽きることがない。アリストテレス、ウェルギリウス、エラスムスを初めとする古今東西の読書人たちの図版やめずらしい写真なども豊富で楽しい。
「最後のページ」で、マングェルは読書の意義を端的に語っている。「私たちは誰もが、自分が何者であり、そしてどこにいるのかを少しでも知ろうとして、自分自身や自分を取り巻く社会を読む。私たちは理解するために、あるいは理解し始めるために読むのである。読まずにはいられないのだ。読むとはつまり、呼吸するのと同じく、私たちに必須の機能なのである」(19頁)。マングェルは、読むことを呼吸と同レヴェルに位置づけて、それなしには人間は生きられないのだと断言している。だが残念なことに、凡人は不断、自分の呼吸のリズムをあまり意識しないし、読むことが生き死ににかかわるなどとは考えない。手間ひまのかかる読書など敬遠して、手軽に得られる情報の海で溺れてしまうことの方が多いのだ。こうして、本当は呼吸と同じように、一生涯を通じて必要で欠かせないはずのものが見失われてしまう。
マングェルの主張は明快だ。自分や自分の位置、自分の生きている社会をきちんとわかって生きている人はいないということだ。生きるということは、自分がわかっていないことに気がついて、わかろうと努めることだ。そのためには、どうしても読むことが必要になってくる。読むことを通じて、わからないですましていたことがわかってくる。読むことは何度でも繰り返されて、そのたびにあたらしい発見の喜びが生れる。それに対して、生きることは繰り返しがきかないし、やり直しもできない。マングェルは、トルコの小説家オーハン・パムークの『白い城』から引用している。「『人生とは一回限りの馬車に乗るようなもので、終わってしまえば二度と再び乗ることはできない。しかしもし、あなたが書物を手にするならば、それがいかに複雑で難解なものであろうとも、それを読み終えた時、望むとあらば、最初に戻ったりもう一度読み直したりして、その難解だったところを理解し、それによって人生も同じく理解できるのだ』」(38頁)。何度も読み返すことで、読み手に変化が現れ、その変化は読み方にも現れ、こうして少しずつ理解が深まっていく。
マングェルが引用するカフカの書簡の一部は、本を読む経験のなかで起こりうることをずばりと指摘している。言われてみれば「なるほどそうだ」と納得する指摘だ。「『要するに私は、読者である我々を大いに刺激するような書物だけを読むべきだと思うのだ。我々の読んでいる本が、頭をぶん殴られた時のように我々を揺り動かし目覚めさせるものでないとしたら、一体全体、何でそんなものをわざわざ読む必要があるというのか?(中略)本当に必要なのは、ものすごく大変な痛々しいまでの不幸、自分以上に愛している人物の死のように我々を打ちのめす本、人間の住んでいる場所から遠く離れた森へ追放されて自殺する時のようなそんな気持ちを抱かせる本なのだ。書物とは、我々の内にある凍った海原を突き刺す斧でなければならないのだ、そう僕は信じている』」(111頁)。カフカが読書に期待しているのは著者との真剣勝負であり、圧倒的な敵の世界に打ちのめされ、痛めつけられ、解体され、ぼろぼろにされる敗北の経験である。カフカの熱望したような、読書による魂の変質にこそ、絶望的で屈折した時間を生きる苦痛が伴うとしても、読む経験に生ずる劇的な一面が示されている。
リルケが読書に求めるものは、カフカとは違う。「『今私は作品のことを考えていません、書物を読み、これを再読反芻していく中で、少しずつ健康が回復しているように思います』」(290頁)。書くことに疲れきったときのリルケにとって、読書は癒しの効果を持っていた。読書に集中する静謐な時間のなかで、リルケの繊細な魂がこうむった傷は癒えていったのである。マングェルは言う。「リルケは、読書しながら、その書物をかつて読んだ人々のことを読み取ろうともしていた」(291頁)。リルケは、多様な読み方を試みることによって、読むことの経験に深さとひろがりを与えた詩人であった。
トマス・ア・ケンピスの言葉が引用されている。「『これまで私は、あらゆる場所に幸福を見いだそうと努めてきたが、幸福感を味わえたのは、小さな書物を持ってどこかの小さな片隅にいる時だけである』」(174頁)。マングェルは、「小さな片隅」の例として、肘掛け椅子、地下鉄、バス、寝室、化粧室などをあげ、「『心地よく読書できるのは、化粧室の中であった』」(同頁)というヘンリー・ミラーの言葉をあげている。この小部屋は、プルーストにとっては、「『一人、誰からも邪魔されずにやりたいこと、つまり読書したり、物思いに耽ったり、泣いたり官能的な喜びを感じたりする』」場所であったという(同頁参照)。本を読むのに広い場所はいらない。身ひとつを支える場所があれば、本は幸福な時間を運んでくる。
「禁じられた読書」では、パピルスの巻物の時代から現代にいたるまでの検閲者による焚書の歴史の断面が描かれている。紀元前411年に、アテネではプロタゴラスの著作が焼かれ、紀元前213年に、始皇帝は領土内のすべての書物を焼きつくそうとした。その後も戦乱に乗じた図書館破壊や、ローマ皇帝による発禁処分などが繰り返されている(307頁参照)。1933年、ゲッペルスは群集が喝采する焚書の場でこう演説したという。「『今晩、過去の猥雑なるもの全てをこの火にくべるがよい。今晩の焚書は、過去の精神がまさに死んだのだということを全世界に示す、実に力強く、偉大で象徴的な行為なのである』」(308頁)。書物にも受難の歴史が重なっているのだ。
マングェルには、『図書館 愛書家の楽園』(野中邦子訳、白水社、2008年)という本もある。「はしがき」のなかの一文が印象に残る。「愛の多くがそうであるように、図書館への愛も学ばなければ身につかない」(9頁)。「終わりに」のなかで、紙でできたなじみ深い世界や言葉で組み立てられた意味のある宇宙としての図書館は、物語を読んで何かを感じとり、詩や哲学を通して理解した内容を、体験や知識や記憶としてとどめる可能性を与えてくれるのだという彼の信念が語られている(293頁参照)。図書館とのつきあいを永続的なものにするためにも、ぜひ読んでほしい本だ。
デヴィッド・L・ユーリンの『それでも、読書をやめない理由』(井上里訳、柏書房、2012年)も、読書の醍醐味を語る1冊だ。ユーリンは、ロサンゼルス・タイムスの文芸批評を担当する記者である。彼は、「エピローグ」のおしまいをこう締めくくる。「わたしは腰を下ろす。静けさを呼び入れようとする。以前よりもそれは難しくなっている。だが、それでもなお、わたしは本を読むのだ」(193頁)。それ(読書)が難しくなった理由は、「日本語版によせて」の冒頭で語られる。携帯電話、Eメール、ブログ、ツイッターなどの絶え間ないざわめきや、過剰ネットワーク生活のせいで、本に集中できなくなったというのだ(194頁参照)。その状況を見つめなおす目的で本書が書かれた。「テクノロジーがもたらすノイズ」(同頁)に汚染された生活の反省と自己批判の書である。
アメリカの現実、自分の思春期の回想、15歳の息子との対話、脳科学の知見、作家論電子書籍の特徴などが自由に語られるが、もっとも興味深いのは第3章「もうひとつの時間、そして記憶」である。瞬時に現れて消えるネット情報を追いかける忙しい生活との対比で、生活のゆとりによって可能になる読書の意義が語られる。「読書は瞬間を身上とする生き方からわたしたちを引きもどし、わたしたちに本来的な時間を返してくれる。今という時の中だけで本を読むことはできない。本はいくつもの時間の中に存在するのだ。まず、わたしたちが本と向き合う直接的な時間経験がある。そして、物語が進行する時間がある。登場人物や作家にもそれぞれの人生の時間が進行している。誰しもが時間との独自の関係を背負っている」(103頁)。読書とは、自分の時間を生きるなかで、同時に物語の時間や、登場する人物の時間、出来事の時間を思考力や想像力を駆使して生きるドラマなのだ。本を読むことは、自分を読むこととも不可分な経験でもある。この種の経験には、感受する力と注意力、深く考える力が欠かせず、読むことを通じてこれらの力はさらに鍛えられる。
ユーリンは、電子書籍市場の拡大にともなう読書の運命、読者と作家との関係を問題視する一方で、「ディスプレイで読書をする人々をみるにつけ、そこはかとなく希望をいだいてしまう」(182頁)という。本を読むという行為のさまざまな可能性を見つめているのだ。
|
| |
アルベルト・マングェル
(Alberto Manguel) [1948-]
1948年、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスに生まれ、ブエノスアイレスおよびイギリスのロンドンで学生時代を送る。フランスおよびカナダに在住(現在はカナダ国籍)。英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語など数ヵ国語を自在に操るポリグロットの作家、批評家として世界的にその名を知られる。小説『異国から来た手紙』ではマッキトリック文学賞を受賞。ほかに随筆集『鏡の中へ』『愛と憎しみの歴史』『世界文学にみる架空地名大事典』(ジアンニ・グアダルーピとの共著、翻訳は高橋康也監訳、講談社刊)など著書多数。―本書奥付より一部抜粋
|
デヴィット・L・ユーリン
(Daivid L. Ulin)
米ロサンゼルス・タイムスの文芸批評・担当記者。2005~2010年に読書欄を担当。同紙のほか「アトランティック・マンスリー」「ネーション」「ニューヨーク・タイムズ・ブックレビュー」などに寄稿している。カリフォルニア大学大学院で創作文芸を教えるほか、カリフォルニア芸術大学客員教授もつとめる。著書に、The
Myth of Solid Ground: Earthquakes, Prediction, and the Fault Line Between Reason
and Faith、編者としての作品にAnother City: Writing from Los Angeles、Writing Los Angeles:
a Literary Anthologyなどがある。―本書奥付より
|
|
|
|
 |
|